 歩行時に非麻痺側の足関節の背屈が起こらないケースが圧倒的に多いのです。
歩行時に非麻痺側の足関節の背屈が起こらないケースが圧倒的に多いのです。
ヒールコンタクトが起こらない。
非麻痺側なのに。
非麻痺側ですから
当然、端座位では、足関節を背屈できます。
でも、歩行時にはヒールコンタクトではなくて足裏全体で接地しているのです。
初めて、このことに気がついた時には自分の見間違いかと思いました。
何度も見直しました。
何人もの方の歩容を確認しました。
やっぱり見間違いなんかじゃない。
このことが意味することは一体なんなのでしょう?
おそらく、安定性を優先して非麻痺側下肢のはたらきを自制しているのだと思われます。
身体は総体としてはたらいている
身体は身体を守っている
私はこのことを確信しています。
いつかどこかで書くつもりでいますが
認知症のある方においても言えることなのです。
非麻痺側のべた足歩き
なぜ、こんなにも明白なことなのに
今まで誰も気がつかなかったのか…
身体を部分として捉え
麻痺側を「修正すべき」対象として捉え
歩行観察はしても
全体をみていなかったことの証しではないでしょうか。
非麻痺側の下肢なのだから「問題」が起こるはずがない。
最初から「非麻痺側は問題ない」として
「見れども見えず」状態だったのではないでしょうか。
そして、もし、そうだとしたら
同じことが他の状況でも起こっているのではないでしょうか
それらの意味することは何なのか…
私たちは科学的という言葉を使う一方で
とても重大なことを見落としてきてしまったように感じられてなりません。





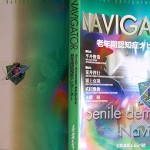




最近のコメント