HDS-Rを施行すると、怒り出してしまう方がたくさんいます。
(怒り出すということも大事な情報ですが)
検査は大事ですが
検査しなくても観察から検査と同等の洞察ができれば
認知症のある方の心身の負担を減らすことができるとずっと思っていました。
そのため
HDS-Rやかなひろいテストをする一方で
日常生活や会話の質的内容や行動との照合をずっと行なってきました。
HDS-Rの項目の意義を理解できるようになり
生活場面への反映についてそれなりに洞察ができるようになり
だんだんと観察だけでもかなりHDS-Rの予測がつくようになり
生活場面への反映についてもわかってきたので
HDS-Rの検査場面でちょっと1工夫することも始めました。
詳細は 「対応に役立つHDS-Rの工夫」 をご参照ください。
ところが、
これだけ認知症の普及啓発がなされている現状でも
実際に働いている職員の中には
「リハに支障がない」「従命可」「会話が弾む」「気遣いができる」「冗談が言える」
という程度の根拠で
「認知症じゃない」「年相応の物忘れ」などと、
安易に無責任な判断をする人がまだまだ多いという現実にびっくりしています。
「ちゃんとお話ができるから認知症じゃない」
という言葉を幾度聞いたことでしょう。
この言葉はその裏側に
「認知症になるとちゃんとお話ができない」
という思い込み・偏見があるからこそ、言える言葉です。
そんなことは決してありません。
HDS-R3/30点の方が
「こんなバカな俺に優しくしてくれてありがとう」と言ったり
HDS-R0/30点の方が
「俺はよ、ここがよ(頭を指さして)こうだから(指をくるくる回す)」
と発言されたりします。
年相応の物忘れと判断された方のHDS-Rは10点
認知機能低下に言及もされず、しっかりした方と言われていた方の
HDS-Rは5点ということもありました。
これだけHDS-Rが低いと明らかに生活に影響が生じいるはずなのに、
認知機能低下が見落とされている。。。
ご家族や生活の支援をする看護介護職は困っているのに
一部のリハ職はまったく気づいていないという。。。
ひとつには
認知症、認知機能低下という概念の理解ができていない職員側の問題がありますし
他方
他者に合わせようとして生きてきた方、他者に合わせるタイプの方は
自主的に起こす行動が少ない場面だと
認知機能低下が目立ちにくいという傾向があります。
たとえば、困った時わからない時には
誰かに尋ねて返ってきた答えの通りに対応する方や
自分から何かしようとはせず指示があるまではじっと待っている方は
その場では「穏やかな方」「良い方」といった判断がなされがちで
記憶の連続性が低下していたとしても
行動特性から表面化しにくいので見落とされてしまいます。
また、俗に言う地頭の良い方、元来認知機能が高かった方は
記憶の連続性が低下しても逆症や計算ができるので
これまた見落とされがちです。
「同居しているご家族は認知機能低下によって生活支援で困っていても
たまに来るご家族には理解してもらえないことも多い」
と言われるゆえんです。
MMSEを施行する時に
MMSEはHDS-Rとは違って、検査項目が記憶だけではない
という前提条件を見落としていると
得点結果だけで判断してしまい、状態を見誤ります。
同じ30点満点のテストでも、
得点結果が同じ20点であったとしても
どの項目で失点してどの項目で得点したかは全く異なります。
実際に
他院でMMSEが10点代後半、疎通も良好で礼節も保持されていた方で
他院からのリハサマリーに認知機能低下への言及がまったくなかった方とお話をしていたら
1分前にした説明を忘れてしまっていたので
HDS-Rをとったら10/30点だったということがありました。
遅延再生も見当識も0点でした。そのかわり計算や語想起は満点だったという方もいました。
得点結果だけで判断してはいけないのです。
HDS-RとMMSEの違いを認識した上で使い分ける
そして、失点項目と得点項目に着目する
わからない時にどんな風に対応するのかということを観察しておくと
日常生活で困難に遭遇した時の行動パターンが予測できて
対応方法を明確化することに役立ちます。






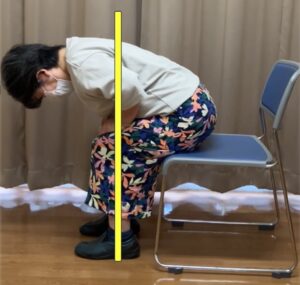

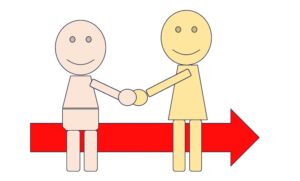

最近のコメント