認知症のある方の食事場面で
協調や協応の困難によって
介助が難しくなるケースは
案外多いものです。
そのような場合に
認知症のある方の食べ方に問題を限定してしまい
介助者側の問題を自覚できないと
あっという間に本当に食べられなくなってしまいます。
そもそも
食事介助の怖さ・奥深さが知られていなさすぎます。
ぜひ、「スプーン操作を見直すべき兆候」をご確認ください。
身体協調性が低下していて
食具や介助者のスプーン操作にうまく協応できない方でも
感覚はちゃんと残っています。
全てを認知症のせいにしないで欲しいなと思います。
不適切なスプーン操作をされた時に
「食べにくい」と感受することはできます。
そして、必死になってなんとか食べようとするか
あまりにも食べにくいので食べられずにいるか
どちらかの行動を起こします。
それらは、多くの場合に
「変な食べ方」「ため込み」「吐き出し」「食事拒否」
という不適切行動として私たち介助者に目には映ります。
そして、ここだけを切り取って不適切行動の改善を目的に
対応を考える。。。というのが現場あるあるですが
そもそも、不適切なスプーン操作をしなければ
認知症のある方の不適切行動も起こらないのです。
起こってしまった不適切行動を
合理的な能力発揮に向けて
行動変容を促すのは大変なことですが、可能です。
ヤマほど経験しています。
HDS-Rが0点、意思疎通困難な重度の認知症のある方でも
行動変容は可能です。
そして、意思疎通も改善されていきます。
ある方は、
頚部前屈しながら上唇を丸めて取り込めるようになり
「なんだ、下を向けばいいんだな」とご自身から言って
嚥下する時に自身で頚部前屈の動きをした方もいます。
衝撃の言葉でした。
「なんだ、下を向けばいいんだな」
この言葉には
どうしたら良いかわからなかったことがわかった
というニュアンスが含まれているからです。
その方は
どうやって食べたら良いのかわからず
食べにくさを食事介助をされるたびにその都度違和感を感じ
この方なりに試行錯誤をしていたのだと思います。
食事介助は
いかに口の中に入れるか
ではありません。
その方がどうやって食べようとしているのかを観察・洞察し
より合理的に食べられるように的確に援助できるのが
食事介助の本質です。
食事介助を的確に行えるということは
同時に
食事という場面で起こっている
環境感受・認識・適応という一連の行為をも
援助することですから
意思疎通困難な方が食べられるようになると同時に
疎通も改善されるのです。
今までの私たちの問題設定が間違っていたのです。
認知症のある方の食べることに関する困難の多くは
ちょっとしたウィークポイントを
拡大再生産してしまった私たちの介助に起因しています。
逆に言えば
食べることの困難を劇的に減らすことは可能なのです。
認知症のある方の食事介助は難しい。
ためこみや吐き出しする人にどう介助したら良いのか?
このような間違った問いには、正しい答えは返ってきません。
今、私たちがすべきことは問いを正すことです。
私たち介助者と認知症のある方との協働作業である
「食べること」を
援助の原点に立ち返って
まず、私たち自身の介助を問い直すことです。
ぜひ、「スプーン操作を見直すべき兆候」をご覧ください。
スプーン操作を見直し
適切な操作を確実に実現することができるようになった時に
認知症のある方の食べ方が変わることを実感できるようになるでしょう。
「食べさせること」と「食べる援助」との違いを
認識できるようになるでしょう。
「どうやって食べさせるか」
「飲ませるか」
という観点で為された対応によって
一時的には効果があるように見えることもあるでしょう。
けれど、短期的なその場の効果はあっても
それらは本当の能力発揮を援助するものではないので
必ず破綻して長期的には一層の困難というカタチで
ご本人にも介助者にもはね返ってくるものです。
それらは実際に現場で起こっているはずなんです。
見れども観えずになっているかもしれないけれど
気がついている人もいるはずなんです。




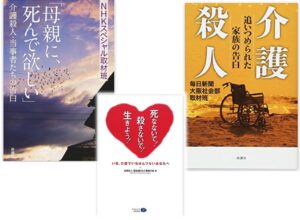




最近のコメント