私がすごく疑問に感じるのは 「その人らしさを大切に」「認知症のある方に寄り添ったケア」 と唱えられることはあっても 実際の実践は、単にハウツーの当てはめをしているだけというケースが多いことです。 「〇〇という時には△△す …
「非習慣的遂行機能の評価」 当院に実習に来る学生さんには、遂行機能の評価は習慣的遂行機能と非習慣的遂行機能の2つを評価するように指導しています。 でも認知症の病態が進行してくると、非習慣的な遂行機能評価の「使えるバッテリ …
「バリデーションセミナー2014のお知らせ」 今年も開催されます。 バリデーションセミナー2014! 平成26年7月19日(土)の東京会場を皮切りに、大阪・福岡・名古屋でも開催されます。 認知症のある方とのコミュニケーシ …
徘徊や暴言、暴力、異食や大声等のBPSD(Behavioral and Psychological Smptoms of Dementia:認知症の精神・行動症状)は、ご本人も介助者も困ってしまいます。 タイトルに引かれ …
以前にある研修会を聴講した時に、他職種の方から講師に対して「認知症のある方に作業選択をどのように考えたらいいのですか?」という質問がありました。 他職種でもこんなに真剣に本質を考えている人がいるのだということを知り、とて …
「認知症本人と家族介護者の語り」ディペックス・ジャパン NPO 健康と病いの語り ディペックス・ジャパンが運営するサイトをご紹介いたします。 認知症の家族介護者35名と7名の当事者のインタビューを動画で視聴することができ …
認知症のある方に出会ったら… 「認知症」という診断名がすでにある方なら、まず最初にADLとコミュニケーションを評価しましょう。 ADLとコミュニケーションのそれぞれについて 何ができるか、できないか。 どこまでできて、ど …
いわゆる暴言、介護抵抗があるAさんとお散歩に行きました。 そろそろ昼食の時間になるので (Aさん、もうじき11時30分になるところですから、そろそろ戻りましょうか?) と私が尋ねた時のAさんのお答えが 「11時30分にな …
農家の90歳のAさん。 車いすに座っているけど移動するのでフットプレートに足をのせてほしい。 そこで職員が言った言葉が「オミアシヲアゲテクダサイ」 Aさんは足をあげることができませんでした。 接遇は、とても大事だと思いま …
2013年が始まり、最初の1ヶ月がそろそろ経とうとしています。 今年もナオミ・フェイルさんが5月に来日してバリデーションセミナーが開催されます。 詳細はこちらをご参照ください。 公認日本バリデーション協会http://w …
Previous
Next

知人から内村鑑三の言葉を教えてもらいました。
「事実の子たれよ。
理論の奴隷たるなかれ。
事実はことごとくこれを信ぜよ。
その時には相衝突するがごとくに見ゆることあるとも、あえて心を痛ましむるなかれ。
事実はついに相調和すべし。
その宗教的なると科学的なると、哲学的なると事実的なるとにかかわらず、すべての事実はついに一大事実となりてあらわるべし。」
本当にその通りだと思いました。
こんなに明確に言語化していた人がいたんですね。
理論とか常識というメガネをかけて見てはいけない。
メガネを外して事実そのままを観るように心がける。
事実が理論や常識として言われていることと反することや
事実同士が矛盾するように見えることでも
必ず見落としていた、隠れていた、一片のピースが見つかり
整合性のある事実としてもう一度現前し直す。
こういうことには、よくよく遭遇しています。
リハやケアの常識として語られていることも
事実の子たる在りようによって
異なる現実として現前し直す。
科学は過去の知識の修正の上に成り立つ学問だし
ましてや、作業療法は実践の科学です。
目の前の対象者こそ最前線。
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/3999

適切なスプーン操作が評価の入り口であるのと同じように
適切な声かけが評価の入り口
適切な声かけができて初めて認知症のある方の能力がわかる。
適切な声かけができないと
対象者の状態像を見誤ってしまいます。
求められているのは
唯一絶対の正しい声かけではなくて
その時その場のその関係性において適切な声かけ
なんだと考えています。
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/3991
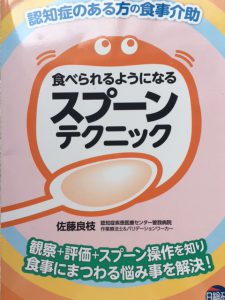
適切なスプーン操作ができて初めて対象者の食べ方、本当の能力がわかる。
適切なスプーン操作は評価の入り口
適切なスプーン操作ができないと評価のドアがくぐれない。
今、目の前に見えていることそのままが事実ではないこともありえます。
事実の一旦しか見えないこともありえます。
かつて
地球は動かないという天動説が常識だった時代がありました。
確かに、空を見上げれば太陽が動いていて私たちの足元は動いていません。
私たちの目の前に見えるのは「太陽が動いている」ということです。
でも、本当は太陽の周りを地球が回っている。
そのことを日々の暮らしの中で直接実感することは叶わないけれど。
だからこそ
観察力と洞察力が大切なのだと強く感じています。
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/3990

2019年、今年も2週間経ってしまいました。
みなさま、どのように新年を迎えられましたでしょうか。
だ〜いぶ長いこと更新が滞ってしまいましたが
記事更新を再開いたします。
改めまして、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/3989

ありそうでないのが目標設定の研修会
今週末、12月22日(土)の午後に
東海道かわさき宿交流館にて目標設定の研修会が開催されます。
目標を目標のカタチで設定できることは、とても重要なのですが、
現実には目標と目的や治療内容との混同が為されていて
そのために余分な混乱、困惑が引き起こされているのは勿体無いことだと感じています。
残席わずか、締め切りまでわずか。
お申し込みの予定のある方はお早めにどうぞ。
詳細は
作業療法総合研究所のサイトの該当ページをご参照ください。
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/3985

聴いてみないとわからない。
認知症のある方が大声を出している時に
「また大声出してる」で終わらせずに
なぜ大声を出しているのか。
その答えが言葉として明瞭に返ってくることもあれば
言葉以外の答えとして返ってくることもある。
聴くのは言葉だけではなくて
認知症のある方の答え方全体を聴く。
耳だけじゃなくて
眼でも観察する。
思いもかけない答えが潜んでいることもある。
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/3981

スティーブ・ジョブズの言葉に
「意図こそが重要」と言う言葉がある。
この言葉の意味を
その都度その都度何回もわかり直している。
認知症のある方への対応について
「援助」なのか、「使役」なのか、という違いはとても大きくて
にも関わらず、実は自覚されにくい。
例えば
入浴でもトイレでも誘導しようというときに拒否されてしまう
ということは、よくあります。
このときに
「誘導しようとしたら拒否されてしまった。
どうしたらいいだろう?」
と言う問いのカタチでは
「拒否されない誘導の方法は何があるだろう?」
というカタチで問いを重ねることになってしまいます。
これでは主語が私たちになってしまっています。
ここでもしも
「誘導しようとしたら、嫌!と言って顔を背けてしまった。
このときに何がこの方に起こっていたんだろう?」
というカタチの問いを立てれば
「何が嫌なんだろう?嫌でないことは何だろう?」
と次へ続けることのできる問いのカタチができます。
この問いは主語が認知症のある方になっています。
どっちだっておんなじじゃん。
とはならない。
意図は相手に伝わってしまう。
例え、明確に表現してもされなくても。
そして、その意図はその後の私たちの行動にも影響を与える。
拒否されないように。。。という観点を重視した関わり
認知症のある方が受け入れやすい方法を探るという観点を重視した関わり
援助なのか、使役なのか
容易にすり替わりがちだからこそ
気持ちだけでは防ぎにくいことだからこそ
意図的に気をつけなくてはならないと思う。
言葉で「認知症のある方に寄り添ったケアをします」
と宣言することも大切かもしれないけれど
個々の実践において「寄り添ったケア」という理想に合致しているかどうか
具体的に検討するとともに
予防できるものは予防していくために
気をつけ方の言語化が必要なのではないかと考えています。
<お詫び>
今回の一連の記事において
誤解を招きかねない表現をしてしまったために記事を削除いたしました。
ここに深くお詫び申し上げます。
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/3978

ここからが問題で
私たちは援助と使役が紙一重ということを
それほど明確には学んでこない。
理想として語られた言葉として聞くことはあったとしても
実際にどのようにしてすり替えが起こってしまいがちなのか
どうしたら少しでも防ぐことが可能なのか
具体的には教えてもらうことがない。
「気をつけましょう」では
行動変容は起こらない。
それはサボっているからではなくて
そうしたくないからというだけでもなくて
気をつけたくても行動を変えることができないことだってある。
認知症のある方の
一見不合理な言動から能力を見出そう
そのように意思として心がけたとしても現実問題できない人は少なくない。
こういう状態は、とても辛い。
なぜできないのか?
それは、過程の具体化が抜け落ちてるから
願えば叶うわけでもなく
唱えれば叶うわけでもない
気持ちだけでは行動変容は起こらない。
自分の実習体験を思い起こせば
あるあるの話なんじゃないかな?
指導者に指摘されたことはわかる。
自分も努力しようと思う。
でもできない。。。
一方で
認知症のある方の立場に立ってみれば
理解してほしい、助けてほしい
と願うだけでなく
自分でできる限りのことはできるようになりたいと願っている。
してもらうのではなくて、自分でできるようになるような援助も願っている。
認知症のある方本人も
周囲の方も
困ってしまう生活障害やBPSDには
その場面にこそ、困りごとというカタチで現れている能力と障害が反映されている。
アフォーダンスの言葉を借りれば
見出されるのを待っている
表面的に
修正したり、改善したり、制圧しようとしてはいけない。
結果としてであっても
能力を否定することになってしまうから。
Permanent link to this article: https://kana-ot.jp/wp/yosshi/3953



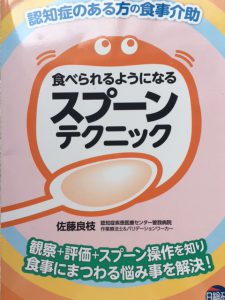





最近のコメント