問題設定の問題、手段の目的化、手段と目的の混同って
リハやケアの分野で往々にして起こっていることです。
その一つが敬語問題だと感じています。
先の記事に絡めて少し補足を。
声かけの工夫について講演で説明すると
「よっしーさんのお話はその通りだと思うんですけど
敬語を使わないと叱られるんです」という声をよく聞きます。
そのたびに
あぁ、またか。。。とガッカリします。
敬語を使うのは手段であって
敬意を示す、伝えることが本来の目的ですよね?
もちろん、そういう方針の施設は
「良かれ」と思っての善意からの方針なのだと思います。
ですが!
「地獄への道は善意で敷き詰められている」
「地獄には善意が満ちているが、天国には善行が満ちている」
という言葉がある通りに善意ほど恐ろしいものはありません。。。
認知症のある方に対して、
幼児に対するような声掛けをしないために
敬語を使いましょうという考え方はわからなくはありません。
でも、問題は2つあります。
ひとつは
幼児のような声掛けは確かに失礼なことではありますが
もしかしたら無自覚のうちに認知症のある方の言語理解力の低下を感受した職員が
分かりやすいように単語中心の声掛けを重ねていた
ただし、無自覚に行なっていたことなので説明できなかった可能性について
検討したことのある施設がどれだけあるのかという問題
もうひとつは
確かに敬語を使うように指導するのは
今すぐにできることの一つなのでしょうけれど
敬語を使うことを奨励するのではなく
敬意を自然と抱けるように職員を養成することについて
検討したことのある施設がどれだけあるのかという問題です。
問題設定を的確に行えないと
得てして解決策も表面的になりがちです。
そして、解決策が有効でないという結果になりがちです。
ここできちんと現実を観察・洞察できなければ
すでに起こっている問題を見逃してしまうことすら起こり得ます。
敬語を使うように奨励するだけでは問題の本質的な解決につながらない
という事象がすでに起こっているはずだと思います。
つまり、声かけが有効に機能しない、意思疎通困難な事例が増えたように見える
という事象です。
優秀な人は、この現実に気がついていると思いますが、
敬語使用によって問題が惹起されてしまうこともあるのだとは
認識できていないのではないでしょうか?
敬語の特徴として
婉曲な表現、長い文章表現という特徴があります。
「御御足を上げてくださいませ」という声掛けで理解できなかった方が
「足、上げて」でちゃんと足を上げられた
というケースがありました。
丁寧に長い文章で伝えたのに
「そんなに長ったらしく言われたってわかんないんだよ!」
と怒鳴られたことがありましたって教えてくださったご家族もいました。
敬語は認知症のある方に理解しにくい言葉となってしまうこともあるのです。
(もちろん、理解できる認知症のある方も大勢いらっしゃいます)
また、
言葉としては確かに敬語を使ってはいても
強い口調で早口で大声で話す職員もいます。
当然、認知症のある方は怒りますが
言葉ではなく、口調や早さや声量が伝えてしまう
本当の感情、本音に対して怒り、理不尽さを感じているのです。
言葉が伝えるコトとノンバーバルが伝えてしまうコトとの乖離に
混乱する方だっているでしょう。
当の職員は(敬語を使っているが故に)
自身のノンバーバルな表現のマズさを自覚せず
認知症だからわからないという自身の誤認を強めてしまう。。。
現場あるあるではないでしょうか?
言葉は伝わって初めて言葉として機能します。
敬意を伝えるどころか
伝わらない敬語に、
言葉としての意味、声かけとしての意味が
どれだけあるのでしょうか。
真に検討すべきは
普通だったら幼児に対するような声掛けをするはずのない大人が
なぜそんな声掛けをしたのかについて
ひとつひとつの場面で具体的に本当は何が起こっていたのかを
事実を事実として振り返り検証する作業だったのではないでしょうか。
私の実践と提案です。
敬意は敬語を使わなくても伝わります。
敬意は言葉以外のノンバーバルな表現で伝えます。
ノンバーバルな表現の伝える影響力については
メラビアンの法則ですでに言われていることです。
その代わり、明確に伝えたい事柄はその方の理解力に応じて
必要であれば単語中心で伝えます。
もっというと
敬意の伝え方を意識するよりも
認知症のある方の能力を見出せるようになれば
どれほど頑張っているのかがわかり
自然に敬意を抱けるようになり
幼児扱いなんてできなくなります。
こちらの方が本来の在り方ではないでしょうか?
遠回りのようでいて
一番確実な方法だと思います。
認知症のある方への話しかける時の姿勢や距離の取り方や
間合い、声量、口調、早さ、表情。。。
ノンバーバルな表出には
敬意もそうでない感情も滲み出てしまいます。
そして、その感情は確実に認知症のある方に伝わっています。
逆に言えば
表面的に敬語にこだわりすぎる人は
肝腎要の敬意を抱いていないという本音を覆い隠そうとしているのでは?
という疑念を抱いてしまいます。
どこまで自覚的かはともかくとして。
そういう意味で考えると
施設の責任者が「敬語を使いなさい」と指導するのもわからなくはありません。
施設としての最低ラインを担保しようとしている表明にはなります。
ただし
働いている職員が敬意を抱けないのに表面的に敬語を使うのは
抑圧であり矛盾です。
現行不一致を要請しても長続きはせずに必ず感情が滲み出てしまいます。
敬語を奨励するのは対人援助職としての入り口としては良いと思いますが
敬語を使えばそれでよし。となってしまうとおかしなことになってしまいます。
誤解を避けるために敢えて書きますが
私は敬語を使うなと言っているわけではありません。
理解できる方には敬語を使っていますし
分離礼を用いて挨拶することもあります。
ただし、敬語を使えば問題が解決するわけではないし
敬語を使うことによって本質的な問題の抑圧・隠蔽につながりはしないか?
敬意を伝えるカタチを指導するのではなくて
敬意を抱けるような養成が先ではないのか?という指摘です。
諸般の事情で
敬意を抱けるような養成が先送りになっている場合に
施設としての最低ラインを担保するための敬語指導であったとしたら
ゴールではなくスタートとして課題設定する
次の課題として将来的に敬意を抱けるような養成について考えていて欲しいものです。
管理者が話を聞いてくれる人であれば
率直にそのあたりを提案してみるのも良いのではないでしょうか。
問題設定の問題、手段と目的の混同とすり替え
いろいろなカタチで現れています。
その具体例が
「なじみの関係を作って誘導に応じてもらう」という考え方・実践であり
「敬語を奨励する」という考え方・実践だと感じています。
「褒めてあげることが大事」というのもそうですね。
おかしいなと感じた時には
問題設定の問題に立ち返る
手段と目的を明確にすることで
問題の本質を把握し、真の解決への道を見つけられると考えています。
プロフェッショナリズムは実践でしか身につかない
プロフェッショナリズムは実践によって磨かれる








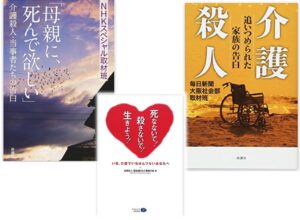


最近のコメント