10月15日(土)に
東京都北区にある北とぴあにて日本シーティングコンサルタント協会さんの主催で開催された
「認知症の理解とシーティング」にて講演と意見交換会に出席してきました。
連絡の窓口となってくださったOさんはじめ社会局のみなさま
どうもありがとうございました。
秋晴れ、行楽日和の中を参加してくださったみなさま、お疲れさまでした。
熱心で前向きな方が多くてびっくりしました。
大勢の参加者の前で質問をしたり、感想を話すことは緊張すると思いますが
最後の意見交換会では、たくさんの方の手が挙がり
あっと言う間に時間が過ぎてしまった感じがしました。
とても良い雰囲気で楽しかったです (^^)
司会を務められたHさんの導入のお言葉が効果的でしたよね。
講師を務められたOさん、Tさん、Mさんのご講演を聴くことができたことも
雑談の中でお話ができたこともとても勉強になりました。
日本シーティングコンサルタント協会さんが
シーティングの知識と技術向上のために系統的に運営されていることに感銘を受けました。
ふだんの臨床もされて、その他の社会的な役割も担当されて、
その上にこのような形での運営を為さっていることに感服です。
単発的な研修会の運営でも大変ですから、系統的な枠組みの中で個々の研修会を企画・運営し
参加者の状況も確認・管理されるのですから。。。
頭が下がります。
これだけのことを為さっているので
中堅・若手の方もどんどん育っていくし
フロアーの方も発言しやすい雰囲気・土壌があるのだろうと感じました。
本当に素晴らしい。
でも誰にでもできることではないとも感じました。
講師として招かれて勉強になることはたくさんありますが
こんな風にして、今までの自分の仕事圏内では出会うことができなかった素晴らしい方々と
出会うことができるのは、本当に役得ですね。
充実感いっぱいの気持ちで帰宅しました (^^)





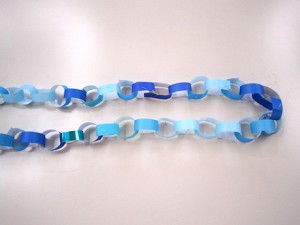


最近のコメント