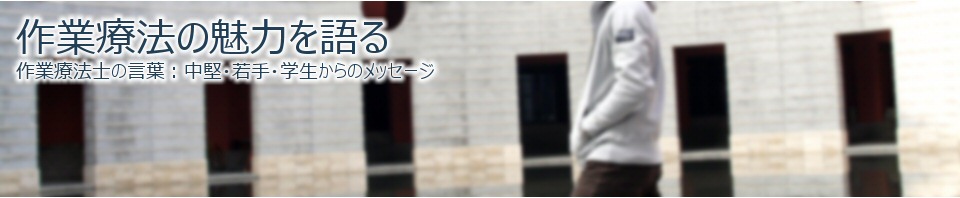伊藤公一OTR(聖テレジア病院)
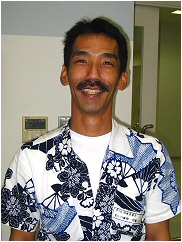 若手(いくつまで?)OTへ 贈る言葉
若手(いくつまで?)OTへ 贈る言葉
作業療法の世界へようこそ。これから書き連ねることは、臨床(小児)→教育(養成校)→臨床(身体障害)と静岡→愛知→神奈川を放浪したOTの戯れ言です。
リレーコラムで様々な人がOTについて語られています。OTとはと?
僕の思う、いややっているOTとは人の生き様そのものではないかと。
OTの仕事には、生身の人と人が織りなすアートの側面があると思います。今流行りのEBOT否定するつもりはありません。たくさんのOTが社会から認められるため、作業療法の質の向上のため、OTを科学とするために取り組まれています。
でも科学にこだわると、他の科学のような再現性の罠に陥ります。いつ、誰がやっても同じ結果(効果)が出る。そうであるなら、僕と他のOTが同じ効果を出すはずです。
でも、現実は違うし、そうだったら、逆につまらないと思いませんか?これこそが、臨床OTの仕事のおもしろさであり、怖さであると思います。
治療テクニックや理論は自分の道具ですが、それを使う自分自身を見つめましょう。今、目の前にいる患者・利用者さんとどんなアートを20分、ないしは40分中で作り出せるか。目で見て、体に触れ、語り、どれだけの情報(評価)を得られるか。
あなた自身・僕自身がOTそのものなのです。自分の全て(自分の趣味や経験が少し考えると)を治療媒体として使用できるし、また、逆に言えば自分自身が治療の効果に影響してしまう。
その楽しさが実感できたら、この仕事について本当に良かったと思えるでしょう。
サービスと地域
OTは人が人にサービスをする仕事です。そして今は目の前の対象者にしか気がつかなくても、その横にいる家族、後ろにある地域をやがて意識するでしょう。
それには、自分が地域の中で生活している一人であると実感する必要があります。
そしてその中で共に生きていく人として、作業療法士として人と関われたらすてきですね。
ものを言うOTでいたい
そんなことを考えながら、今、臨床の現場で仕事をし、学生指導や非常勤講師、県士会役員そして高次脳機能障害の患者・家族会の世話人をしています。
やっている中で、僕はものを言わない人や言えない人に成り代わるなんて意識しているわけではありませんが、自分が感じ、考えていることを職場で、学校で地域であらゆる機会に話そうとしています。
自分のテリトリーはリハビリテーション科だからとか病院だからとか、考えて線を引いてしまったら、自分自身や患者さん、家族の可能性をそこで狭めてしまう。『自分のしたことは「疾患別リハ」ではなく「脳血管作業療法」「運動器作業療法」として請求したい。』とか『地域の小さな病院でもリハのサービスを受けたい』とか。
言ったことが全てむくわれることはないけど、言ったことで初めて考えてもらえることもあります。
不言実行では、やらなくてもわからないけど、有言実行ならやらなきゃ言われる。「偉そうなこと言って、何もしてない」と。
僕は人間って楽を求めるものだと思うし、自分自身がそうだから、自分を追い込むために「ものを言うOTでいたい」という姿勢をとり続けようと思っています。
多分、これは僕のことをよく理解してくれる仲間や先輩がいるからできていて、その点で恵まれていると思います。
最後に「好奇心を持って生活すること」
実習学生にOTの資質で大事なことは何ですかと聞かれることがあります。その時の答えの一つがこの言葉です。
先ほど言ったようにOTっていろんなことが治療媒体として使える。そのためには自分自身のアンテナを高くして、専門領域や病院・施設の中にこだわらず、何でも1回は経験してみる姿勢は大事かなって思います。自分の限界とあきらめないで、一人じゃないから!
おもしろきこともなき世をおもしろく