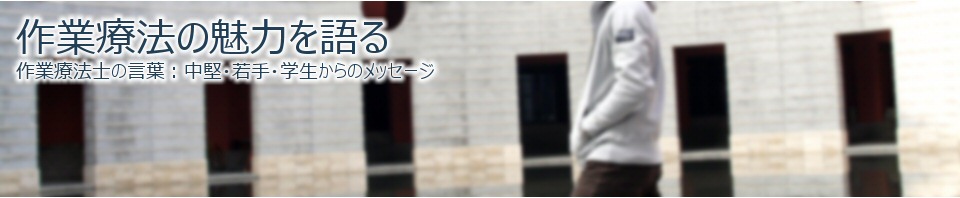冨永渉OTR(国際医療福祉大学小田原保健医療学部))

文書を作成していて、「作業療法」と打たなければいけないところ、タイプミスをして「作業慮法」(さぎょうりょほう)と打ってしまうことが時々あります。このような経験がある人は、恐らく私一人ではないでしょう。作業療法士の資格を取ってから四半世紀過ぎてもなお、「作業慮法」とタイプミスをする度に「作業療法」について慮り(おもんばかり)ます。
1963年に我が国最初の作業療法士養成校として、国立療養所東京病院付属リハビリテーション学院が東京の清瀬市に設立されました。その2年後、1965年6月に「理学療法士及び作業療法士法」が制定され、1966年に第1回国家試験が実施され、同年に日本作業療法士協会が設立されました。ちょうど今から60年前のことで、作業療法士国家試験も今年は「第60回」になります。日本で作業療法が誕生してからの年数は、人でいうところの「還暦」にあたります。還暦は、十干十二支(じっかんじゅうにし)の干支(えと)がひと廻りし、生まれた時の干支に戻ったことことになります。もう一度生まれ変わって出直すことを意味するそうで、赤いちゃんちゃんこを着て祝うのも、この「赤ちゃんに戻る」という意味を表しているそうです。
私が作業療法士になった約30年前では、多くの人が病院に就職していましたが、現在の勤務先である作業療法士の養成校にいると、最近の新卒者の就職先が多様なことに驚かされます。身体、精神、老年期、発達、就労支援、など、人数の偏りはあるものの幅広い分野に卒業生は就職していきます。学会に行っても、若い人たちは様々な新しい角度で作業療法を捉え、実践し、その報告を聴くことができます。学校や企業内で作業療法を実践しようとする取り組み、自身で起業される方など、これまでの作業療法のフィールドではあまり聞くことがなかった現場に活躍の場を広げられています。
60年でリハビリテーションにおける作業療法の位置付けは確固たるものになりました。これからは、これまでの60年で培ってきたフィールドにおける作業療法の質を更に深め、高めると共に、新しく広がりつつある作業療法のフィールドにおいても実績を積み重ね、より多くの人に作業療法を届けなければなりません。新しくとも古くとも、私たちは「人がより良い生活を実現するための支援」が生業です。60年の作業療法の歴史の中で、その半分ほどを私自身は並走して経験してきたことになりますが、次の還暦に向けて、新しく始まる作業療法の世界で、若い人たちが次にどのような驚きの作業療法を展開してくれるのか、とても楽しみでもあります。