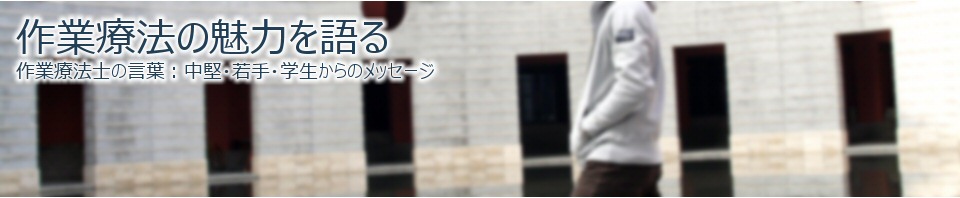私は高校を卒業し、すぐに作業療法士養成校に通いだしました。高校在学中の作業療法のイメージは、趣味的活動を治療手段とするということしかありませんでした。
私は高校を卒業し、すぐに作業療法士養成校に通いだしました。高校在学中の作業療法のイメージは、趣味的活動を治療手段とするということしかありませんでした。
養成校に入って様々な勉強をしていくに従って、当初持っていた作業療法へのイメージが変わりました。
作業療法に対してということもあるでしょうが、人を見る目自体が変わったと思います。人と関わるということは単に好き嫌いでは片付けられない、もっと深いものだということをこの4年間で学んだと思います。
最終的に進む道は身体障害領域か精神科領域のどちらかになるわけですが、どちらを選んだとしても、人と関わる姿勢に変わりはないと思っています。
人と関わる第一関門としてまず、態度が挙げられます。4回に渡る臨床実習を経て、態度は評価されるものだということに気づきました。「つもり」では態度として他人の目に映らないのです。
自分の立場を弁えてそれ相応の振る舞いが必要となってきます。これは社会に出る上で必要不可欠なことであり、学生と言う身分を越えて、一人間として学んだことです。
次に会話が挙げられます。これも臨床実習にて、患者さんを目の前にして会話の内容につまるということが多々ありました。なぜ会話に困るのか。それは自分に引き出しがないからだと思いました。
様々な人と関わることや経験は立派な財産であると思います。経験を通して得ることや学ぶことがあり、人と接することや世の中の動きに対して様々な興味を持ち、学校で学んだことが相まって、それらが治療手段のヒントとなったり会話の材料となったりもすると考えられました。
多くの経験をし、様々な知識を持ち、会話やアイデアとして活かせる人が作業療法士になる上ではとても大きな力を持つのだと思います。
このように、入学前は活動のように媒介となるものが治療手段だと考えていた私は、作業療法士養成校に入学し、学校生活を送り、様々な人と関わっていくにしたがって作業療法のイメージが変わり、現在は作業療法を「自分と言う人間を治療手段とした、その人その人の長所や短所を存分に活かせるもの」だと感じるようになりました。
この感じ方は人各々だと思うのであくまで私の意見ですが、作業療法士養成校で学んだことによって、人と関わる姿勢や、自分自身の在り方を見つめなおす機会となり、今後作業療法士として働く上での礎となったと思っています。
(2005年12月現在,神奈川県内の養成施設に在籍,4年生)