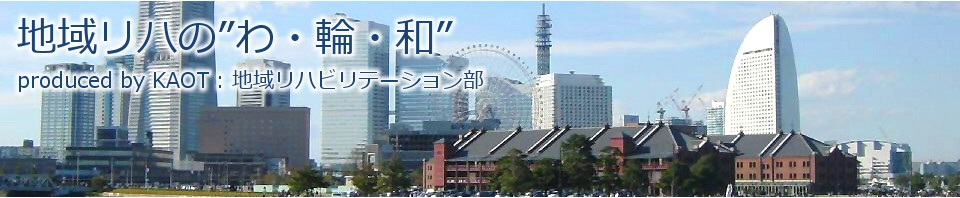シリーズ「認知症の作業療法」 ベテランOTへのインタビュー
特定医療法人社団同樹会 結城病院 川口淳一先生
認知症の作業療法
《プロフィール》
養成校卒業後、長崎市内の病院に勤務し、中枢疾患や整形疾患の高齢者を対象にリハビリテーションから在宅訪問まで一貫した援助を行う。その後、北海道富良野市の介護老人保健施設へ赴任。施設ケア改善の取り組みに加え、重度認知症高齢者のワークショップ開催、高齢者とのコミュニケーションを通してその声に耳を傾けた細やかなエッセイ集『リハビリテーションの不思議-聴こえてくる高齢者のこころの<こえ>-(青海社)』の執筆など、意欲的に活動。3年前より茨城県に移り、現職。はじめに、川口先生にとっての、認知症の作業療法との関わりについてお聞かせください。
卒業後すぐに勤めた病院は、いわゆる老人病院で、入院患者の大多数が認知症の方でした。その当時は、認知症は「リハビリの阻害因子」だと捉えられていて、「認知症があるから、リハビリできなくても仕方がないね」という言葉が、当たり前に交わされるような状況にありました。今とは随分違います。でも「それでよい」とはとても思えないですよね。OTとしての認知症との関わりを話す前に、僕自身の幼い頃の話をしましょう。
自分で「役割」を作る
僕が中学1年生の時に亡くなった祖父は、かなり進行した認知症の状態でした。いわゆる「動ける認知症」です。僕が小学校高学年だったある日、祖父は、何十年と手塩にかけて育ててきた庭の草木を、植木バサミで片っ端から切ってしまいました。家族は「何してるの!じいちゃん」と慌てて止めに入ったのだけれど、動ける人だから、そう簡単には止められない。辺りに切るものが何もなくなったら、今度は、飼っていたセキセイインコを捕まえて、そのしっぽまで切ってしまう。僕が「じいちゃん、何でそんなことする?」と聞くと、祖父は「暑かろう」と答えました。祖父は、生い茂った草木が暑そうに見えたから、涼しくしてあげようとしたのでしょう。何でも「切る」という、その行動の出方は、社会的には受け入れ難いものがあるけれども、祖父なりの理由があっての行動だったのです。
僕ら兄弟が、それよりももっと幼い頃、祖父の家に遊びに行くと、必ず正座して、小一時間ほど戦争の話を聞かされました。それが聞き終わったら、アイスキャンディを買ってもらうというのが、お決まりで、我慢して聞くのです。でも、大きくなるにつれて、アイスキャンディなんて自分で買えるし、遊びにいっても自分のしたいことをするようになって、祖父から戦争の話を聞こうとはしなくなりました。祖父はきっと、家の中で、これといった役割もなく過ごしているうちに、徐々に認知症が進行していったのだと思います。
だけれども、祖父はなんて「逞しい」のでしょう。生活の中に役割がなくなってしまったというのに、役割を自分で作ってしまうのだから。暮らしの中に人に役立つことがなかったから、何の疑問もなく、そのような行動をとっていたのでしょう。
病院にいる患者さんも、祖父と同じ思いをしているはずです。「この方はリハビリできないから寝ているしかない」という医療が行われているなんて、そんなのは絶対にダメだと、22歳のOTになった僕は思いました。
家族としての経験が、OTとしての立ち位置に繋がったのですね。
祖父は、本当はもっといろんな話をしたかっただろうし、もっと人の役に立ちたかったのだろうと思います。祖父の思いに気付くことができたから、OTになってからも、患者さんの思いに気付こうとすることができたのだと思います。
病院内は、エレベーター、車いす、ベッド。その環境はどこをみても、その方の今までの生活とはかけ離れています。この環境の中で、この方々の暮らしを、いかによくできるだろうか。その病院は、一生その場で暮らすような方の多い病院だったのですが、ここが自分のホームグラウンド、と思えるようにする作業療法って、どういうものなのだろうか、と模索しました。
それらの気付きや思いを、作業療法の実践にどのように活かしていったのでしょうか。
「なぜ」に向き合う
色々なことを試してきたけれど、それが自分の中で体系づけられたのは、北海道の老健でのことでしょう。施設に入所している認知症の方々の、一見不可思議な行動、いわゆるBPSDの理由を個々に推理していきました。個人の行動には必ず理由があるはず。その理由を推理していこうと、スタッフ同士で多くの話し合いを持ちました。「なぜ」に向き合うのです。
ケアプラン立案のカンファレンスを毎月開くのですが、その時に看護・介護からOTに対して、「この人、こんな行動があるのですけど、どうしたらいいのですか」という質問をされていました。僕はそれに対して、自分なりに知恵を絞って「こうしてみたら」とアドバイスをしていたのだけれども、大体うまくいきませんでした。打率でいえば1割くらい。ひどいものです。そういった経験から、認知症の人たちと向き合うときには、「どうすればよい」からではなくて、「なぜそういった行動がみられるのか」ということにしっかり向き合わないと、絶対に解決に結びつかないということに気付きました。だからこそ、カンファレンスは「なぜ」を話すことに徹底しました。職種は関係なく、みんなで推理しました。
認知症の方であっても、相手によっては出方を変えるし、リハビリの時はいい顔するけど女性スタッフには辛辣だなんてこともある。そういった個々の事例に対して、スタッフの考えを家族に相談・確認しながら、徐々に関わりの糸口を見出しました。
ある入所者の男性は、人の部屋に入ってはタンスを荒らしていました。自分のものだったらまだしも、他人のタンスを荒らすものだから、これは問題です。当然、他の入所者やその家族からはクレームがきます。どうしてそんなことをするのだろう?その方の気を紛らわせようとして、あの手この手を尽くしてみても、一向に状況は変わりません。ある日、自宅の奥様にタンス荒らしの行動について相談すると、「それ、納屋の整理してるんだわ」と、ぴたっと言い当てました。その方は、長年農家をしていて、離農して認知症状がでた後も、必ず毎日納屋で道具の整理をしていたそうです。そして帰ってくると奥さんのいれる温かいお茶をすすって一息つく。その方には、日課としての「納屋整理=仕事」があったのです。しかし、老健には納屋はありませんでした。仕事場のない状況で、自分で何とかして「仕事」「役割」を見出そうとしている。その行動がタンス荒らしだったのでしょう。でも、仕事をしても達成感・役割感としてのピリオドを打てない。なぜなら仕事をしても、いつものお茶が出てこないのだから。
行動の理由が徐々に見えてきて、よくよく振り返ってみると、その方が荒らしたタンスはすべて、納屋と同じ開き扉のタンスでした。引き扉には一切、手を付けていません。これは間違いない。スタッフで考えたのは、それならもっと納屋らしいところがあると、掃除道具棚の片付けを毎日行ってもらうことを考えました。そして一仕事終わると、いつもと同じようにお茶をだすのです。
掃除道具棚の片付けはその方の日課として定着し、以前のように人のタンスを荒らすことはなくなりました。
チームで「なぜ」を考えることで、介護や看護スタッフの様子も変わってきましたか?
行動には理由がある
その方の一見不可思議な行動の理由がわかると、ケアする側は、やさしくなれます。ある女性の方はティッシュペーパーをたたんで集め続けている方がいました。これは「収集癖」とも言われます。その方は「お姉ちゃんが鼻を垂らしているの」といつも話していました。「お姉ちゃん」とは、その方の娘さんのことなのか、妹さんのことなのか、誰なのかは、はっきりしませんでした。でも、その方は「お姉ちゃん」のために、ティッシュをたたんでいる。
スタッフの中には「また集めてる!」と、怒るような対応をする方もいました。しかし、鼻を垂らしているお姉ちゃんのために、いつでもティッシュを使えるようにしている、その方の思いに気付くことができるようになると、「これだけあれば、お姉ちゃんも安心よね」と声をかけるようになっていきました。
生活歴を通して、その方の行動のあり方を理解していくことは大切ですね。
「なぜ」と考える幅を広げる
その通りですね。でも、「なぜ」を考える時に忘れてはいけないことは、認知症の方だからといって何でも生活歴によるものと考えてしまうことは危険だということです。認知症の方は、あるがまま語れないがゆえに、病気や不調の発見、対処が遅れることは少なくありません。内科的な問題や、神経生理学的な視点をしっかりと身につけて関わることが基本です。「なぜ」と考ける幅を広げるためには、生活歴をより深く踏まえた関わりができる、ことも大切ですが、医学的な視点をもつことも同様に大切です。
現在の勤務先である身体障害領域の病院における、認知症の方との関わりについて教えてください。
ケースを通して、認知症の方との関わり方を伝える
今勤めている病院は、急性期から慢性期まで幅広く対象とする病院で、僕は主に回復期に関わっています。先日、院内で調べたところ、リハビリをしている方の56%の方に認知症状があり、回復期でも46%の方に認知症状があることがわかりました。つまり、認知症のことを理解した上でなければ、ここで仕事をすることは難しいと考えています。
老健に勤めている頃は、一度関わりを持つと、最後までその方の生活支援に責任を持つという意識がありました。つまり、その方とその症状と向き合うことを考えます。しかし、病院は退院させることが何より大切。もっとふさわしい場所があるでしょうという立場です。薬剤の使い方も違います。何より違うと感じていたのは、認知症の方の行動を理解しようとする姿勢のスタッフが、リハスタッフの中であっても少ないということでした。
あるリハスタッフは「認知症があるので拒否されました。今日はリハビリ室に連れて来られませんでした」と言いました。僕の新人の頃の光景が思い浮かび、未だに『認知症はリハビリの阻害因子』という考えが残っているのかと、愕然としました。
そこで、まずは自分が率先して、関わりにくいと思われる方、暴力的な行為がある方などを担当しました。なかなかうまくはいきませんが、あれこれと試していく中で、その方がまた歩けるようになったり、リハビリを通して関わり方がみえてくるケースはたくさんいます。関わることすらできない、という状況から、関わることはできるようになるわけです。
まずは、川口先生がお手本と言いますか、関わり方を他のスタッフに伝えることから始めたのですね。
チームのみんなが同じ目線をもつ
とくに病棟では、認知症の方を「困った人」と捉える向きがありました。これは夜間の大変さなども考えると確かにそうかもしれません。しかし、認知症という1つの脳の病気を持つ「人」として周りが関わるのが本来なのです。忌み嫌われるような人物として捉えられてしまうのは、あまりに悲しいと思いました。
その後、院内で認知症の勉強会を始め、現在も続けています。強制参加にはせず、どの職種でもどうぞ、という形で実施しています。最近では、かなり多数の看護師が参加してくれるようになり、意識が変わりつつあると感じます。最近の勉強会では、問題が多いと捉えられやすい方々を対象としてOTの小集団訓練を実施し、その様子をビデオ撮影したものを使用しました。ビデオを多職種で観察しながら、参加者がその時した表情の意味を考えたり、普段みられている行動の理由を考え、話し合いました。
この3年間で、スタッフからの「あの方は無理です。関われません」というような相談は確実に減っています。見方やケアを変えることで、その方の反応が変わるということを、一人ひとりのスタッフが、日々成功体験として蓄積してきた結果がでてきたのだと思います。
- 病院、老健、そして今また病院でご活躍されている川口先生ですが、場所がどこであっても変わらない、ということでしょうか?
もちろんです。どこでも変わらないですよ。していることは同じです、いつも。
では次に、川口先生が、認知症の方との関わりで最も大切にしていることを教えて下さい。
生活に足りないものを補う
僕は「生活」という作業を5つに分けて考えています。1つはADL。これがなくては、人は生活できない。2つめに役割や仕事。3つめは遊び。これがないと非常につまらない生活になってしまう。4つめは人間関係。一人で生きていけるわけがない。そして5つめに休養。この5つのどれかが0(ゼロ)になると、自分の今の暮らしに足りないものは、人は無意識のうちに補おうとするものです。
例えば僕らだって、知らない土地に引っ越して寂しい思いをしていると、友達や親と長電話をすることで人間関係を補います。学生さんであれば、試験前に時間がないというのに本屋さんで自分がわくわくするような雑誌を立ち読みしてしまったり、無性にカラオケに行きたくなったり、なんてことがありますよね。それは生活に、遊びが足りなかったら、どこかで補おうとしているのです。
入所したばかりの方が、翌朝から徘徊が止まらなくなる、ということがあります。徘徊、それだけを見れば、歩き回っているだけのようにも見えますが、その行動には必ず理由があるはずです。知っている風景も、いつもの役割もない、見慣れた顔もいない。その姿はまるで、何かを探しているようにも見えます。
僕たちは、生活に足りないものがあれば、自ら補う手段を持っています。しかし、それを持っていない方々が目の前にいるのです。ですから、その方の生活に「足りない部分を補う」という意識をもつことが大切なのです。ADL、役割・仕事、遊び、人間関係、休息の全てが100%満たされている人はいません。でも、この5つが「ある」ことが大切なのです。決して0(ゼロ)にしてはいけません。
5つの視点から「生活」をしっかり見ていくことで、その方に対して支援すべきことが見えてくるはずだし、支援することが何もない、なんていうことは絶対になくないです。
生活感を失わない支援
向上できるADLは向上させて当然です。でも、だからといってADLだけが満たされていれば人は「生活している」といえるでしょうか?食事して、トイレにいって、寝て、たまに着替えて、、、そんなの風邪引いたときの生活でしょう?それを何とも思わないのは絶対におかしいと思っています。だからこそ、OTが支援していくべきことがあるのです。例えベッド上であっても「生活」があるようにと僕は思っています。その人の生活感を失わない支援が大切なのです。
本当に無反応?
無反応、なんて言葉が使われますが、そもそも刺激されているのかというと、刺激が入力されていない状態にあることが多いのが事実です。刺激されていないのだから、反応していないのは当たり前。いろんな感覚刺激を与え、本当にやるだけのことをした上で、その方が無反応なのでしょうか。「できることが何にもない」なんていうことは、そうそうないことです。しかし、「反応もないし、(活動に)参加しても意味がなさそうだから、やめときますね」といった言葉がケア場面では当たり前に交わされています。
僕は、感覚刺激を入れることで、変わっていく人たちを数多く見てきました。観察する力で、その方の反応を見出し、それを増幅し、スタッフや家族に伝えていく。そうするとスタッフや家族の関わり方、つまり刺激の量も質も変わってきます。「ほら、こうすればちゃんと手を握るんだから」なんて風になっていきます。
本人の微弱な反応に、こちらが如何に気づくことができるか。そしてそれに対して、刺激を返すことができるか。そのことを常に意識しています。
次に、これまでのご経験から、印象的なケースとの関わりについて教えてください。
役割を0(ゼロ)から1へ
今の病院での経験を話しましょう。結城は「結城紬」が有名で、ユネスコの無形文化遺産に指定されています。僕が担当したある90歳代の女性は、若い頃に結城紬の職人さんをしていました。着物を織るほどの腕前だったようです。今回の入院の理由は内科疾患で入院後に廃用症候群が進行した状態にありました。
関わっていく中でADLの次に考えたのは「役割」でした。生活のほとんどの時間をベッド上で過ごして、生活の中に「役割」が何もない。つまりその方の役割は0(ゼロ)の状態だったのです。紬の職人さんとしては既に引退していましたし、それを役割として行うというのは難しいだろうな、と思いました。ようやくリハ室に顔を出せるようになり、まずはじめにその方にお願いしたことは、僕と手を繋いでリハ室を1週することです。リハ室を1周しながら、若いスタッフたちに「頑張ってるね」と一声掛けて、肩をポンポンと触りながら、リハ室のスタッフ全員を激励するという役割を、1日2回、その方にしてもらいました。何より良かったのは、それを言われた側の若いスタッフ達のリアクションで、「ありがとう」とか「待ってましたよ」などの嬉しい気持ちをその方に伝えてくれました。毎日2回の役割を繰り返しているうちに、その方はリハ室に行く時間の前になると、自分でベッドから起きているようになりました。おそらく、僕が思うに「私も捨てたものじゃない」という気持ちになってくれたのではないかと思います。それは、その方の病院内での役割が0から1になった瞬間であったと思います。
自ら役割を作り出した瞬間
退院の際に、その方の娘さんがリハ室を訪れてくれました。そして「おばあちゃんから頼まれました」と言って、箱に入った結城紬の財布を取り出しました。その方が昔織った着物の一部を使って、娘さんに作らせた物だそうです。以前は病室で寝てばかりいた方が、OTである僕を喜ばせたいという思いから、娘さんに着物を指定し、財布を作るように指示してくれたそうです。そのようにして、その方と娘さん、そして、その方とOTである僕との人間関係が紡がれていきました。
僕の手を引いてリハ室を歩く、という役割は、OTである僕が想像した、病院内での役割に過ぎないものでした。 しかし今回は、その方が、自分自身で人の役にたちたいと、作り出した生活の中での役割です。それはOTとして、何より嬉しい経験でした。
最後になりますが、神奈川県OT会の若手OTに、メッセージをお願いいたします。
対象となる方々も、自分たちも、同じ生活者なのです。施設生活とか、病院生活とか、家の中だけとか、ベッド上とか、色々な生活があります。でも「生活」と言っている以上は、同じでなくては不公平です。病気だから、高齢だからといって、一人ぼっちでもいいとか、何もしなくていいとか、そんなことは決してないのです。それだけは忘れて欲しくないと思っています。あたり前の「生活者」であるという視点を忘れずに、やってみましょう。
- 川口先生、心のこもった貴重なお話を本当にありがとうございました。
(文責:地域リハビリテーション部 河村)